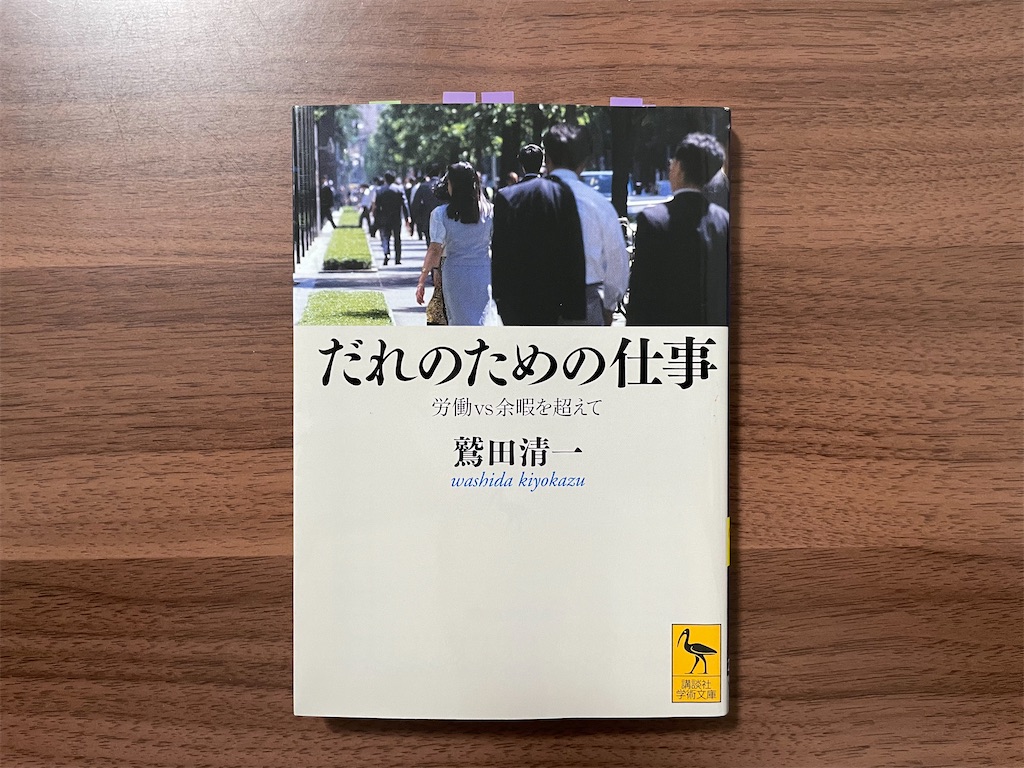
難しい本でした。
ただ、それでも心に残る箇所がいくつかあったので、ここに書き残しておきます。
『だれのための仕事』感想
「はじめに」の章で書かれた言葉に、まず引き付けられた。
じぶんで意味を与えないことには意味が見いだせないというのは、ひとつには、じぶんの存在が他人にとってじゅうぶんに意味のあるものになっていないということを意味する。
またそのように問わないでいられないというのは、いまのじぶんの生活のどこかに、そのような問いを発生されてしまうような空白があるということを意味する。
ないかよくわからないままに、とにかく、ある欠落、ある喪失の感情が、たぶんそのひとのなかで滲むように広がりつつあるのだろう。
これに続いて、労働の歴史を紐解きながら仕事に関する著者の考えが展開されていく。
労働者の実態
読み進めていくと、途中でデヴィッド・リースマンという人の引用があった。
労働者の実態の話だ。
労働者にとっては仕事に積極的な意味など求めていない。労働者が求めているのは、仕事をもつことによって自分自身の存在意義を明らかにし、定期的に働くことで生活を規則正しくしたいだけだ。
なるほどそうかもしれない。
僕はこれだけ仕事の内容や環境について関心が強いのに、他の人の話を聞くと、どうもそこまで考えていないように思えたからだ。
内容なんて気にしていないのか、気にする余裕がないのかはわからない。ただ、多くの人は仕事に対してそれほど積極的でないように僕にも感じられる。
僕はそれが不思議でならないのだけれども。(^^;)
意味を求めてしまう心理
仕事に意味を見出そうとする僕の感情はおかしいのではないか……
そう思ったけれど、本のなかでおもしろい話があって、これは間違っていないのだと知った。
スターリンのバケツの話である。
かつてスターリンの時代に、バケツの水を別のバケツに移し、そのあとまた元のバケツに戻すという行為のはてしない反復が拷問として課されていた
やはり人は、意味が見いだせないことをやらされるのを嫌うらしい。
でも、そのあとで著者は「ところが」と続ける。
ところがその仕事の意味は仕事のなかですぐに見えるかというと、仕事の意味が、あるいは仕事をしているひとの顔が、あるいは仕事の結果がもつ意味が、とても見えにくいのが、現代社会のような高度のシステム化した社会の特質なのである。
仕事の意味がわかりにくい。みんなの顔がみえる場所で働いているわけでもないから、人の表情もわかりにくい。極めて細かく分断された仕事を任されるから、仕事の結果も見えにくい。
システム化されすぎているがゆえに、全体としての意味がボヤケてしまうのだ。
働いているとき、僕もこれは感じていたから共感した。
さいごに
正直に書くと、この本はけっこう読みにくかった。ほとんどは流し読みで終えた。難しめの本だったと思う。
幸い仕事に関する本は世の中にたくさん出ているし、僕自身の関心もあるのでこれからもこのテーマについては読書していこうと思う。
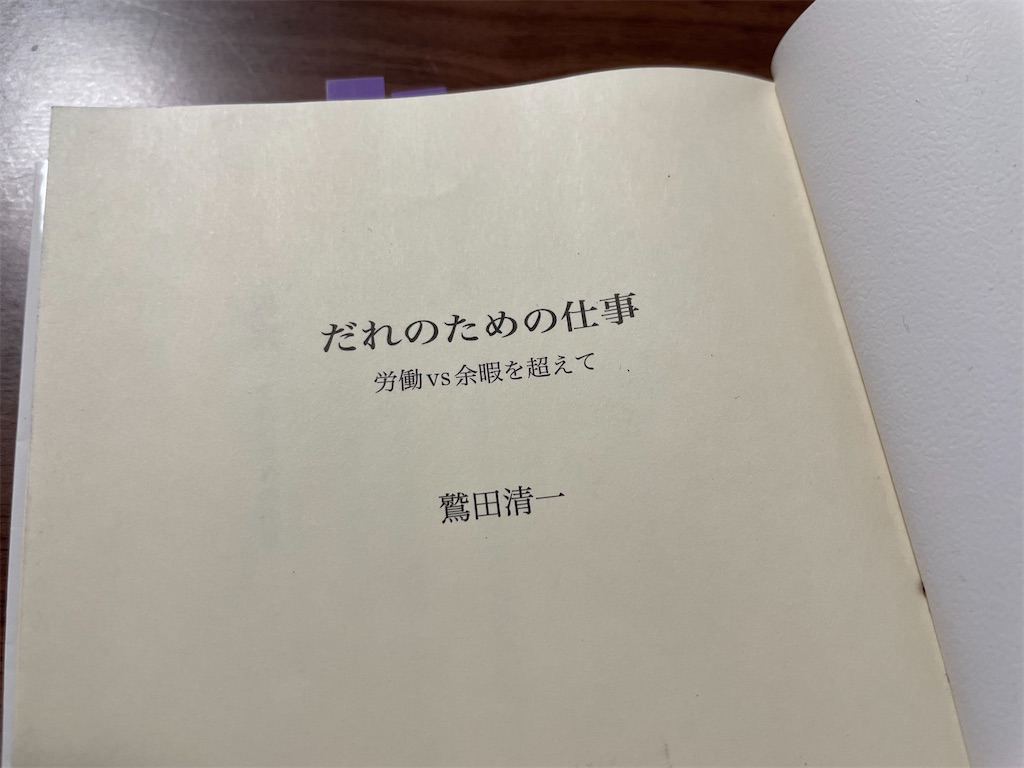
今回はほとんど流し読みだったけれど、それでも自分にとってのポイントとなる箇所はいくつかあったから、それだけでもまとめておきたくて書いた。
気になる人がいれば図書館にでも行って借りるといいと思う。
今回はこのへんで。
ではまた。